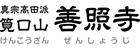| 寺院名 | 筧口山 善照寺 |
|---|---|
| 本山寺 | 真宗高田派専修寺 |
| 創建 | 長禄年間(1457年頃) |
| 所在地 | 三重県鈴鹿市庄野町28番2号 |
| 敷地面積 | 792坪(2613.6㎡) |
| 建築床面積 | 本堂101.5坪(334.95㎡) 庫裏・鐘楼堂・山門あり |
| 建築様式 | 本堂9間4面入母屋造り 木造瓦葺 |
歴代住職
| 第一世 | 善正法師(ぜんしょうほうし) |
|---|---|
| 嘉永7年(1854年)6月15日安政の大地震の始まりと言われる、伊賀上野地震によって、庫裏が倒壊し、青年衆徒2名が圧死。記録を紛失し、元禄以前の過去帳が不明となり、第二世~第九世までの住職名が判明しない。 | |
| 第十世 | 恵亮 |
| 第十一世 | 慧澄 |
| 第十二世 | 智丈 |
| 第十三世 | 秀泰 |
| 第十四世 | 蓮暁(れんぎょう) |
| 第十五世 | 蓮暐(れんしょう) |
| 第十六世 | 蓮橋(れんきょう) |
| 第十七世 | 滋元(じげん) |
| 第十八世 | 智徳(ちとく) |
| 第十九世 | 英揮(えいき) |
長禄年間(1457~1460)に平田地内筧口と称する所に、善正法師(大永3年入滅)が善照寺を開基した。初めは天台宗であったが、高田派第十世 真慧上人の化導によって真宗高田派に改宗し、今日に至っている。
庄野町は東海道五十三次の一駅として発展した。宿駅の繁昌と関連して、九間四間、入母屋造りの本堂は寛政年間(1795年頃)に建立された。
第十二世 智丈 第十三世 秀泰は学僧として有名であり、鈴鹿市の無形文化財である大念仏踊の歌詞『一ツとかしょ ひとり生まれて ひとりゆく さても はかなき この世かな』以下略。は智丈、又は秀泰の作と伝えられていて、昭和9年 第十六世 蓮橋が訂正して現在の歌詞となっている。
沿革
| 長禄年間(1457~1460頃) | 善正法師により善照寺を開基 |
|---|---|
| 寛永4年(1792) | 梵鐘鋳造 |
| 寛永年間(1795頃) | 現在の九間四間、入母屋造り本堂建立 |
| 弘化5年(1848) | 本堂瓦を造る(本堂南の角、鬼瓦に弘化5年申5月と彫刻あり) |
| 嘉永4年(1851) | 本堂再建(昭和23年4月 本堂の東南しぶき修繕の際に発見。東の柱に『嘉永亥年 アサキ部中分村 大工七蔵建之』と書かれている) |
| 嘉永7年(1854) | 伊賀・上野地震により庫裏が倒壊。元禄以前の過去帳等を紛失する |
| 昭和18年(1943) | 国の命により梵鐘供出 |
| 昭和35年(1960) | 鐘楼堂 建立 |
| 昭和36年(1961) | 梵鐘再鋳 |
| 昭和46年(1971) | 山門再建 |
| 昭和49年(1974) | 集中豪雨により、庄野6番町以下の町内が浸水。当寺も本堂・庫裏が床下、その他の建物が床上浸水の被害に会う |
| 昭和57~58年(1982~83) | 国道1号線の拡張により、鈴鹿河川敷の共同墓地を移転 |
| 昭和58年(1983) | 本堂屋根 瓦ふき替え及び修理 |
| 平成9年(1997) | 本堂横 書院 建立 |
| 平成16年(2004) | 蓮橋上人50回忌の際を記念して、本堂風雨除けの板塀を作り替える |
| 平成17年(2005) | 庫裏 建て替え |
| 本堂雨風除け板塀 作り替え | |
| 平成20年(2008) | 第十八世 智徳住職 就任 |
| 平成27年(2015) | 第十九世 英揮住職 就任 |
| 平成30年(2018) | 鐘楼屋根 瓦ふき替え及び修繕 |
| 平成31年(2019) | 本堂内部に納骨堂を建立 |
| 令和2年(2020) | 本堂正面 スロープ設置 |
| 令和3年(2021) | 本堂屋根 小規模修繕 |
| 令和4年(2022) | 本堂雨樋 修繕 |
| 令和5年(2023) | 第二十世 英鳳 得度 |
| 令和6年(2024) | 七里講 退講 |